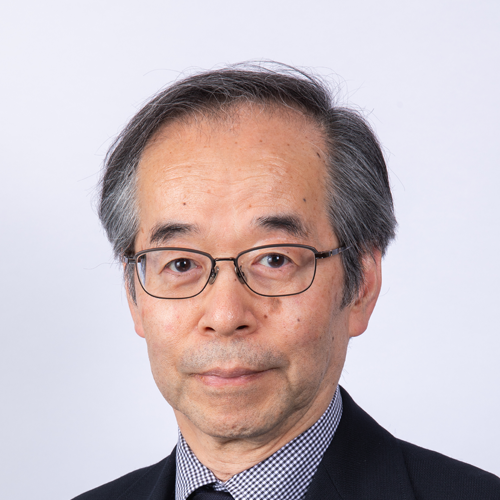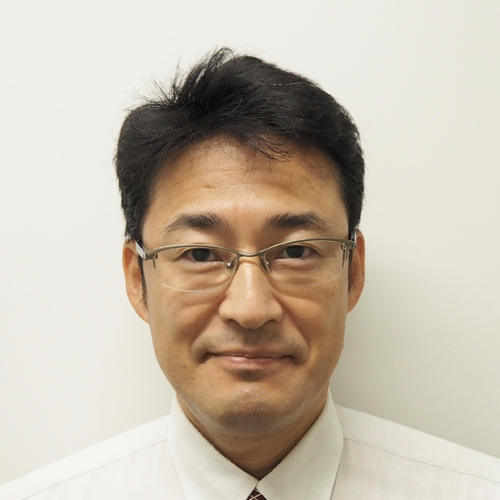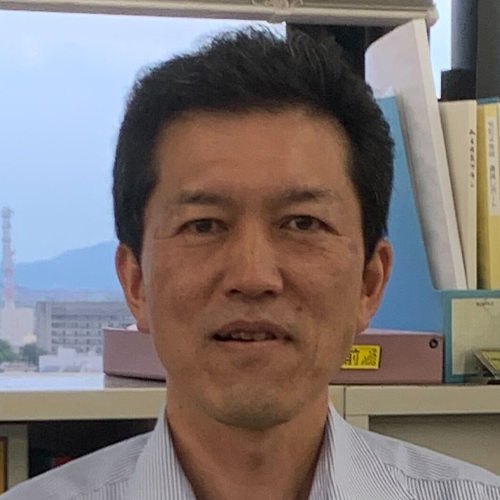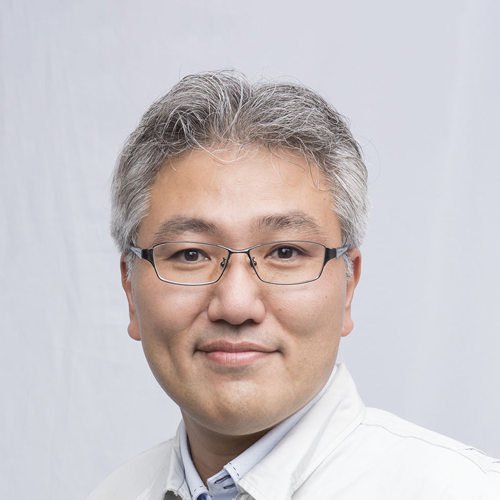国際コンファレンス
2023年6月27日(火)
コンファレンス聴講をご希望の方は下記の来場事前登録ページからお申し込みください。
お申し込みはこちら
※講演内容及び講演者は変更になる可能性がありますのでご了承ください。
※海外講演者につきましては、和訳テロップまたは同時通訳を予定しています。
コンファレンスルーム1
| 10:00 - 10:30
JDKA-1
無料
|
デジタル臨調における規制見直し ~テクノロジーマップ・技術カタログの整備と技術検証~

須賀 千鶴
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会事務局 参事官
|
|
|
| 10:45-11:15
JDKA-2
無料
同時通訳付
|
IITデリー校IHFCのドローン技術パークとそのインパクト

Prof. Subir Kumar Saha
Project Director of IHFC and Professor at IIT Delhi, Mechanical Engineering, IIT Delhi, IHFC (Technology Innovation Hub of IIT Delhi)
|
|
|
|
11:45-13:00
JDSS-4
有料
同時通訳付
|
次世代エアモビリティの運航管理の1展望-欧州大規模プロジェクトから観る

市川 芳明
一般財団法人総合研究奨励会日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 幹事 / 多摩大学大学院 客員教授

<キーノートスピーチ>
David Batchelor
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)
Chief External Affairs and Communication

Robin Garrity
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)Senior External Affairs Officer

Cengiz Ari
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)U-space Programme Manager

Ludovic Legros
U-ELCOME/EUREKA Project Manager, EUROCONTROL

中村 裕子
一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 事務局次長
|
|
|
| 13:30 - 14:30
IASS-2
有料
同時通訳付
|
~LV4のその先へ。ドローンポートが新たなドローン産業を拓く鍵となるか~

津川 清一
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 国際関係担当ディレクター /
ISO/TC20/SC17/WG1 コンビーナ

田中 健郎
ブルーイノベーション株式会社 取締役 常務執行役員
「ISO5491の内容、作成経緯、今後の発展」

Filippo Tomasello
Senior Partner, EuroUSC Italia ltd.
「ISO5491と他の国際標準との関係」
(オンライン登壇)

Sissel Thorstensen
CEO, Management, DragonFlyPads
「ドローンポート製造会社としての国際標準の活用」
(オンライン登壇)
|
|
|
| 15:00-17:00
自治体フォーラム
無料
|
地域の特性を活かした次世代空モビリティへの関わり方
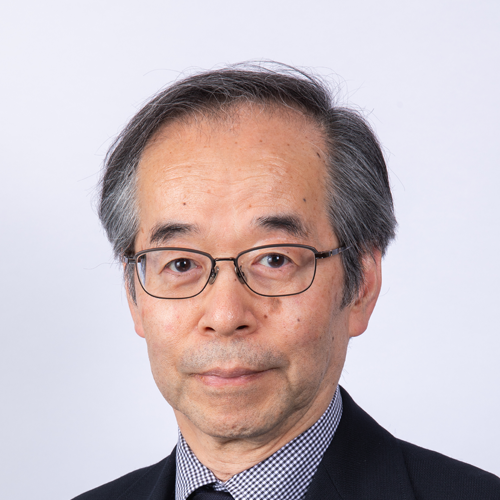
鈴木 真二
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 理事長

<キーノートスピーチ>
岩本 学
株式会社日本政策投資銀行 産業調査部 調査役
「次世代エアモビリティの登場と地域社会へのインパクト」

前川 学
兵庫県 産業労働部 新産業課 課長
「空飛ぶクルマの社会実装に向けた取組み」
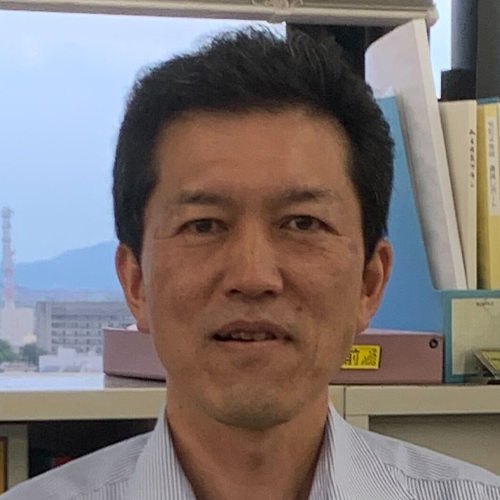
川本 英司
三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 課長

岡田 明之
愛知県 経済産業局 革新事業創造部 イノベーション企画課 事業創出グループ 課長補佐
「空と道がつながる愛知モデル2030」

山田 俊郎
岐阜県 商工労働部航空宇宙産業課 航空宇宙・ドローン産業連携監
「岐阜県のドローン産業に関する取り組み」

永野 喜代彦
長野県 企画振興部 DX推進課 課長

松本 尚征
福島県 商工労働部 次世代産業課 主査
「福島県における取組紹介」
|
コンファレンスルーム2
|
|
| 12:00 - 12:30
EP-3
無料
|
ドローンの機体を超短納期で開発!カーボンファイバー3Dプリンタ

トーマス・パン
マークフォージド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
|
| 13:00-13:45
MPS-4
有料
|
安心・安全なドローンの運用に向けて

石井 守
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 電磁波伝搬研究センター 研究センター長
|
|
|
| 14:10-14:55
MPS-5
有料 |
ドローン、次世代エアモビリティに係るJAXAの研究
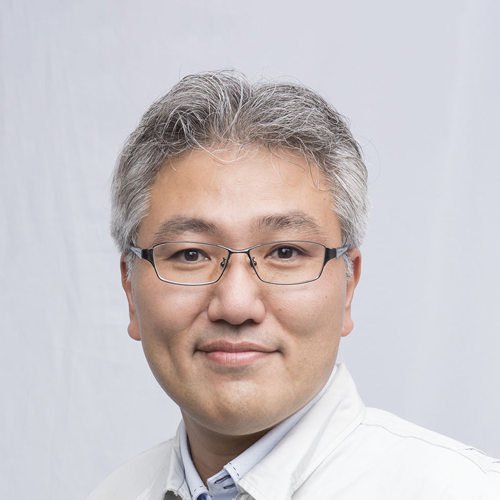
又吉 直樹
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 航空技術部門 航空利用拡大イノベーションハブ ハブ長
|
|
|
| 15:20-15:50
EP-4
無料
|
スマートドローンが目指す次のステージ

博野 雅文
KDDIスマートドローン株式会社 代表取締役社長
|
|
|
| 16:10-16:55
MPS-6
有料
|
農業におけるドローン活用の現実と最新未来像について
|
|
|
コンファレンスルーム1
|
JDKA-1 10:00-10:30 無料
|
デジタル臨調における規制見直し ~テクノロジーマップ・技術カタログの整備と技術検証~

須賀 千鶴
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会事務局 参事官
|
|
JDKA-2 10:45-11:15 無料
日英同時通訳付
|
IITデリー校IHFCのドローン技術パークとそのインパクト

Prof. Subir Kumar Saha
Project Director of IHFC and Professor at IIT Delhi, Mechanical Engineering, IIT Delhi, IHFC (Technology Innovation Hub of IIT Delhi)
|
|
JDSS-4 11:45-13:00 有料
日英同時通訳付
|
次世代エアモビリティの運航管理の1展望-欧州大規模プロジェクトから観る

市川 芳明
一般財団法人総合研究奨励会日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 幹事 /
多摩大学大学院 客員教授

<キーノートスピーチ>
David Batchelor
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)
Chief External Affairs and Communication

Robin Garrity
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)Senior External Affairs Officer

Cengiz Ari
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)U-space Programme Manager

Ludovic Legros
U-ELCOME/EUREKA Project Manager, EUROCONTROL

中村 裕子
一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 事務局次長
|
|
IASS-2 13:30-14:30 有料
日英同時通訳付
|
~LV4のその先へ。ドローンポートが新たなドローン産業を拓く鍵となるか~

津川 清一
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 国際関係担当ディレクター /
ISO/TC20/SC17/WG1 コンビーナ

田中 健郎
ブルーイノベーション株式会社 取締役 常務執行役員
「ISO5491の内容、作成経緯、今後の発展」

Filippo Tomasello
Senior Partner, EuroUSC Italia ltd.
「ISO5491と他の国際標準との関係」
(オンライン登壇)

Sissel Thorstensen
CEO, Management, DragonFlyPads
「ドローンポート製造会社としての国際標準の活用」
(オンライン登壇)
|
|
自治体フォーラム 15:00-17:00 無料
|
地域の特性を活かした次世代空モビリティへの関わり方
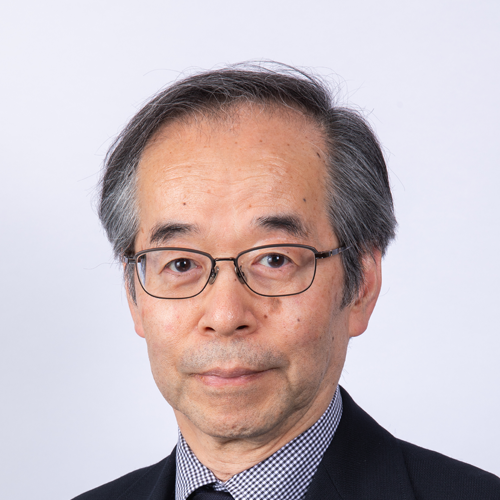
鈴木 真二
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 理事長

<キーノートスピーチ>
岩本 学
株式会社日本政策投資銀行 産業調査部兼航空宇宙室 調査役
「次世代エアモビリティの登場と地域社会へのインパクト」

前川 学
兵庫県 産業労働部 新産業課 課長
「空飛ぶクルマの社会実装に向けた取組み」
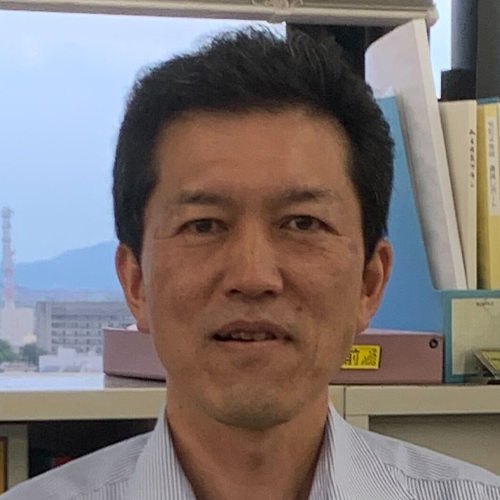
川本 英司
三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 課長

岡田 明之
愛知県 経済産業局 革新事業創造部 イノベーション企画課 事業創出グループ 課長補佐
「空と道がつながる愛知モデル2030」

山田 俊郎
岐阜県 商工労働部航空宇宙産業課 航空宇宙・ドローン産業連携監
「岐阜県のドローン産業に関する取り組み」

永野 喜代彦
長野県 企画振興部 DX推進課 課長

松本 尚征
福島県 商工労働部 次世代産業課 主査
「福島県における取組紹介」
|
※講演者名 敬称略
コンファレンスルーム2
|
EP-3 12:00-12:30
無料
|
ドローンの機体を超短納期で開発!カーボンファイバー3Dプリンタ

トーマス・パン
マークフォージド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
MPS-4 13:00-13:45 有料
|
安心・安全なドローンの運用に向けて ー私たちがお役に立てることー(仮)

石井 守
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 電磁波伝搬研究センター 研究センター長
|
|
MPS-5 14:10-14:55 有料
|
ドローン、次世代エアモビリティに係るJAXAの研究
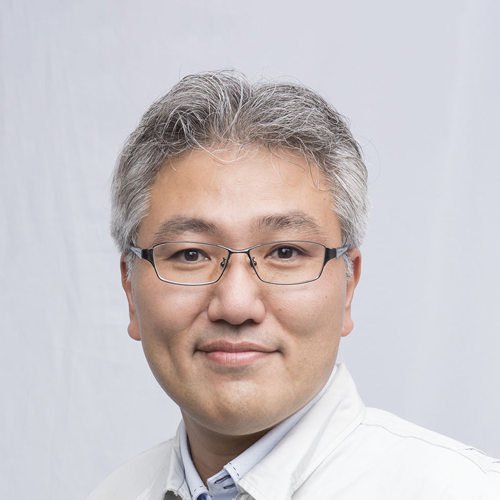
又吉 直樹
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 航空技術部門 航空利用拡大イノベーションハブ ハブ長
|
|
EP-4 15:20-15:50 無料
|
スマートドローンが目指す次のステージ

博野 雅文
KDDIスマートドローン株式会社 代表取締役社長
|
|
MPS-6 16:10-16:55 有料
|
農業におけるドローン活用の現実と最新未来像について
|
※講演者名 敬称略
鈴木 真二
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 理事長
プロフィール
1953年岐阜県生まれ。79年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。(株)豊田中央研究所を経て、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻教授を定年退職後は、東京大学名誉教授、東京大学未来ビジョン研究センター特任教授(現職)。工学博士、専門は航空工学。日本航空宇宙学会会長(第43期)。国際航空科学連盟(ICAS)会長など。著書に、『飛行機物語』(筑摩書房)、『現代航空論』(編集、東京大学出版会)、『落ちない飛行機への挑戦』(化学同人社)などがある。
須賀 千鶴
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会事務局 参事官
プロフィール
2003年に経済産業省に入省し、気候変動、資源外交、クールジャパン戦略、コーポレートガバナンス、FinTechなどを担当。2016年より「経産省次官・若手プロジェクト」に参画し、150万DLを記録した「不安な個人、立ちすくむ国家」を発表。2018年7月より初代・世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター長、2021年7月より現職。東京大学法学部卒、ペンシルバニア大学ウォートン校経営学修士(MBA)。
Prof. Subir Kumar Saha
Project Director of IHFC and Professor at IIT Delhi, Mechanical Engineering, IIT Delhi, IHFC (Technology Innovation Hub of IIT Delhi)
プロフィール
1983年インド・ドゥルガプール工科大学機械工学科卒業後、インド・IITカラグプル校で修士号、カナダ・マギル大学で博士号を取得した。1991年、博士号取得後、株式会社東芝のR&Dセンター(日本)に入社。日本での約4年間の実務経験を経て、1996年よりIITデリーにて勤務している。
市川 芳明
一般財団法人総合研究奨励会日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 幹事 /
多摩大学大学院 客員教授
プロフィール
1979年東京大学工学部機械工学科卒業、日立製作所エネルギー研究所入社。2020年4月退職。IEC TC111(環境規格)前国際議長、IEC ACEA(環境諮問委員会)日本代表、およびISO TC268/SC1(スマートコミュニティ・インフラストラクチャ)の前国際議長, ISO TC 323(サーキュラーエコノミー)WG2国際主査。技術士(情報工学)。
David Batchelor
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)
Chief External Affairs and Communication
プロフィール
David Batchelorは欧州連合(EU)の航空交通管理研究・技術革新パートナーシップであるSESAR 3 Joint Undertaking(SJU)の渉外・コミュニケーションチーフ。 SJUのコミュニケーション活動、ステークホルダーとの関係、国際業務を担当。 2012年にSJUとFAAのNextGenプログラムとの間のリエゾンオフィサーとしてSJUに初めて参加し、4年間ワシントンDCの駐米欧州連合代表部を拠点に過ごした。
それ以前は、欧州委員会のモビリティ・トランスポート総局(DG MOVE)に勤務。 2008年から2012年まで、航空と環境に関する政策に携わり、ICAOのCommittee on Aviation Environmental Protection(CAEP)の欧州連合オブザーバーを務める。2003年から2007年にかけては、2007年に署名されたEUと米国の「オープンスカイ」航空輸送協定を交渉した欧州委員会のチームの主要メンバーであった。
オックスフォード大学で政治・哲学・経済学の学士号を取得後、英国Civil Aviation Authorityのエコノミストとしてキャリアをスタート。
Robin Garrity
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)Senior External Affairs Officer
プロフィール
Ludovic Legros
U-ELCOME/EUREKA Project Manager, EUROCONTROL
プロフィール
Cengiz Ari
シングルヨーロピアンスカイ航空管制研究共同実施機構(SESAR)U-space Programme Manager
プロフィール
中村 裕子
一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 事務局次長
プロフィール
自動車会社を経て、東京大学(航空イノベーション総括寄付講座)へ。2013年、工学博士(東京大学)取得、2017年8月より特任准教授。2023年4月からは一般財団法人総合研究奨励会所属。イノベーションマネジメント、ドローンリスク管理、低高度空域運航管理(UTM)の研究に従事。
津川 清一
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) 国際関係担当ディレクター /
ISO/TC20/SC17/WG1 コンビーナ
プロフィール
2020年5月1日 ブルーイノベーション株式会社入社
2020年10月23日 ISO/TC 20/SC 17 WG1 コンビーナ就任
2022年3月1日 JUIDA入社
田中 健郎
ブルーイノベーション株式会社 取締役 常務執行役員
プロフィール
2019年10月ブルーイノベーションに参画し、2022年7月より現職。以前はシャープ株式会社およびナブテスコ株式会社で主に海外営業に従事し、営業企画や事業戦略を担当。日本企業のグローバルな事業展開を志とし、ブルーイノベーションの戦略と実行に携わる。
Filippo Tomasello
Senior Partner, EuroUSC Italia ltd.
プロフィール
1969年からイタリア空軍に勤務。1984年からENAV(イタリアの航空管制プロバイダー)に勤務。その間ICAO各組織の構成員もしくは議長を務める。2000年から2015年までヨーロッパの各組織(EUROCONTROL、DG-MOVE、EASA)で勤務。EASAの業務を航空管制、空港、UASに拡大し、ICAO UAS研究委員会の議長を務めた。中国とイタリアの大学で航空規制の教授を務めている他、EuroUSC Italiaのシニアパートナー、JAA-Training OrganisationのUAS学部マネジャーを務めている。
Sissel Thorstensen
CEO, Management, DragonFlyPads
プロフィール
デジタルマーケティングとホテル買収の専門家・起業家。2020年にバーティポートを製造するDragonflypads社を創設し、第1世代のバーティポートを開発した。パリを拠点にして、バーティポートに関するISO委員会の重要なメンバーとなっている。
岩本 学
株式会社日本政策投資銀行 産業調査部 調査役
プロフィール
2012年に株式会社日本政策投資銀行に入行。2019年より航空宇宙室にて国内外の航空機関連メーカー向けファイナンス業務や空飛ぶクルマを含む航空宇宙関連のイノベーション分野の調査業務を担い、2022年より産業調査部にて次世代エアモビリティの社会実装実現のための活動を推進。
個別講演
空飛ぶクルマやドローンなどの次世代エアモビリティは空の移動・輸送を身近にし、様々な社会課題を解決する可能性を持つ。本講演では次世代エアモビリティが地域社会に与える影響について考察するとともに、足元の国内自治体の取組を紹介する。
井手 潤也
長崎県 企画部 デジタル戦略課 課長
プロフィール
前川 学
兵庫県 産業労働部 新産業課 課長
プロフィール
1993年兵庫県庁入庁。教育委員会を振り出しに、課税収税、県予算編成、
市町村行政、地方交付税等の業務経験を経て、2023年4月から新産業課長に着任。
休日は山歩きを楽しむ。
個別講演
空の移動革命をもたらす新たなモビリティとして「空飛ぶクルマ」への関心が高まっています。これまで兵庫県は多様なフィールドを活かしてドローンの社会実装で先駆的な取組みを進めてきました。その知見を生かし「空飛ぶクルマ」においても2025大阪・関西万博を契機に社会実装を先駆けて進めるべく取組みを推進します。
川本 英司
三重県 雇用経済部 産業イノベーション推進課 課長
プロフィール
民間企業勤務を経て、平成4年に三重県庁入庁。
製造業を中心に産業支援業務に長年携わり、令和5年4月から産業イノベーション推進課長に着任。
岡田 明之
愛知県 経済産業局 革新事業創造部 イノベーション企画課 事業創出グループ 課長補佐
プロフィール
2003年愛知県庁入庁。
福祉、選挙、防災、民間企業派遣、人事業務を経て、2023年4月から現職。
山田 俊郎
岐阜県 商工労働部航空宇宙産業課 航空宇宙・ドローン産業連携監
プロフィール
1995年岐阜県入庁。東京大学、通信・放送機構(現NICT)の研究所に派遣され、バーチャルリアリティシステムに関する研究に従事。2003年より、県の試験研究機関において、VRの産業応用やものづくり中小企業のIT活用の研究に従事。近年は電磁環境試験室の立ち上げ・運営に携わる。2022年4月より現職。
個別講演
岐阜県には航空機を製造する企業が多く集積しています。県ではその特徴を活かして、ドローンの利活用に関する支援はもとより、ドローンの機体関連産業の振興も推進しています。今年3月に策定した「岐阜県ドローン開発・製造・活用方針」による県の支援策および県内でのドローンに関する取り組みを紹介します。
永野 喜代彦
長野県 企画振興部 DX推進課 課長
プロフィール
2004年経済産業省入省。資源・エネルギーや自動車産業政策、東日本大震災後の福島県浜通り地域の復興支援業務等に従事。
2022年7月からは長野県に出向し、現職。
松本 尚征
福島県 商工労働部 次世代産業課 主査
プロフィール
2010年4月に福島県庁に入庁
採用1年目の時に東日本大震災を経験
その後、福島県立医科大学派遣、総務部職員研修課を経て2019年4月より現職
福島ロボットテストフィールドの立ち上げ時期から施設の整備・運営業務に従事
個別講演
福島県では、東日本大震災および原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業回復のため、国家プロジェクトである「福島イノベーション・コースト構想」に基づき、ロボット・ドローン関連産業の集積を推進しています。福島ロボットテストフィールドを核とした、開発実証の支援を始め、各種補助制度など、空飛ぶクルマを含めたドローン関連産業の集積に向けた取組をご紹介します。
戸國 英器
VFR株式会社 開発部 取締役
プロフィール
1998年ソニー㈱入社。2014年よりVAIO株式会社にてPC開発、スマートフォン開発PLを経て、新規事業、スタートアップ企業との開発に従事。2020年よりVFR株式会社開発部部長、2023年4月より取締役就任。
トーマス・パン
マークフォージド・ジャパン株式会社 代表取締役社長
プロフィール
1989年 米3DSystems社の研究開発員
2002年 3Dシステムズ・ジャパン(株)代表取締役社長
2010年 プロトラブズ合同会社社長
2018年 GEアディティブ日本統括責任者
2021年 マークフォージド日本統括責任者
2022年 日本法人代表取締役社長に就任、現在に至る。
石井 守
国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 電磁波伝搬研究センター 研究センター長
プロフィール
1993年京都大学大学院理学研究科卒(理学博士)
1993年-1994年 独Max-Planck Institute fuer Aeronomie客員研究員
1994年通信総合研究所(現情報通信研究機構)入所
1998年-1999年 米国アラスカ大学フェアバンクス校客員研究員
2021年より現職
又吉 直樹
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 航空技術部門 航空利用拡大イノベーションハブ ハブ長
プロフィール
1997年東京大学大学院工学系研究科航空学専攻修士課程修了.同年,科学技術庁航空宇宙技術研究所入所.2008年英国リバプール大学リサーチフェロー.現在,国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構航空利用拡大イノベーションハブ長.ドローンや次世代エアモビリティの航空交通管理に関する研究等に従事.
博野 雅文
KDDIスマートドローン株式会社 代表取締役社長
プロフィール
2004年にKDDI入社後、長くセルラーネットワーク構築に関わる企画・開発業務に従事。
2014年より、商品端末の無線通信プロトコル開発に従事後、2016年より、モバイル通信技術に関する知見を活かしドローン事業化を推進。
2022年にKDDIスマートドローン株式会社代表取締役社長に就任、現在に至る。
田中 克憲
株式会社ナイルワークス 取締役COO
プロフィール
筑波大学システム情報工学研究科博士前期課程修了。2007年住友商事入社。エネルギー資源分野を中心にクロスボーダーM&AおよびPMI業務に従事。2015年から急速に立ち上がるスマート農業分野の取り込みをはかるべく、国内スタートアップ投資を行う。2021年よりナイルワークス社取締役に就任。
JDKA-1 講演概要
デジタル臨時行政調査会では、「デジタル原則」に基づいて既存規制の見直しを推進しています。本年度は、ドローンやセンサー等の技術活用が期待される規制領域を対象に、技術検証事業も実施予定です。また、技術発展に応じた規制の不断の見直しや技術の社会実装を促進する仕組みとして、「テクノロジーマップ」や「技術カタログ」等の整備にも着手しています。本講演では、これらの取り組みについてご紹介します。
JDKA-2 講演概要
IITデリーのIHFC(I-Hub Foundation for Cobotics)は、インド政府科学技術省から資金援助を受けている技術革新ハブです。講演では、IITデリーのソーニーパットキャンパスに設立されたドローンテクノロジーパークの特徴について紹介します。この施設はドローンの技術的側面、主に様々な機械部品、電気アクチュエーター、コントローラー、プログラミング、ビジネスなどについて、若者を訓練し、起業支援する施設です。また、本展示会にインドから出展するドローン企業を簡単に紹介し、興味のある方にはマッチング支援もいたします。
JDSS-4 講演概要
今後、技術の発展とともに、ドローンやeVTOLの社会実装が進む中で、特に需要が高くなると思われる都市の空と、その交通管理の未来はどうなるでしょうか。
その展望の1つとして、デジタル・ヨーロピアン・スカイを目指す欧州の官民パートナーシップSESAR 3 JUが、そのコンセプトから研究プロジェクトの最近の成果までご紹介します。
このセッションは、いち早く制度化を進めている欧州の取り組みについての概要を伝える基調講演から始まり、その後のパネルセッションでは、キーノートとは別にSESAR 3 JUの中心メンバー3名をお呼びして、ICAOや欧州の規制、標準化、研究の文脈でのSESARの取り組みの紹介から、航空交通管制を研究する国際機関EUROCONTROLとの広範な協力関係、SESARの研究プログラムまで、より詳しく紹介してもらいます。さらに、こうした欧州の取り組みとその未来に相対して、日本の都市部の空はどうなるのか、日本でUTM標準化や自治体連携に取り組むモデレーターとパネリストで、議論を深めていきたいと思います。
IASS-2 講演概要
現在ISO/TC 20/SC17 WG1では、電動貨物UASの垂直離着陸のためのインフラストラクチャと設備に関する国際規格(ISO5491)の作成作業が最終段階に入っている。これは、150 kg以下のVTOL電動貨物UASを扱うVertiportが自動離着陸オペレーションを実現するために必要なインフラストラクチャと機器の最小要件を規定するものである。本講演では、ISO5491の概要と経緯や関連するISO規格を説明した後、サービス事業者としての標準化の使い方や今後のドローンポートの展開についてパネリスト間で議論する。
自治体フォーラム 講演概要
ドローンや空飛ぶクルマなど次世代空モビリティーは、地域の課題解決に貢献すると期待されている。就労人口減少による人手不足、高齢化による移動困難化、自然災害激化のほか、産業振興への期待もある。本セッションでは、各地の動向に精通され日本政策投資銀行の岩本氏の基調講演の後、各地の自治体から、地域の特性を活かした次世代空モビリティーへの取り組みをご紹介いただき、その期待と課題を議論したい。
EP-3 講演概要
生産機レベルのカーボンファイバー3Dプリンタを導入活用したことで、ドローン部品を従来の金型成形では一か月ぐらいかかっていたところをたったの1~2日でできるようになった。同3Dプリンタを複数台導入した結果、たったの90日間で、1機あたり30パーツもある試作ドローンを30機分も製造するなど、ドローンの機体開発における大幅な期間・コストの削減を実現した事例について、質疑応答スタイルで解説いたします。
MPS-4 講演概要
情報通信研究機構では、情報通信に関する唯一の国立研究機関として様々な研究を行っております。講演ではその中から特に、電磁波研究所が進めるレーダ・ライダによる気象計測技術、ドローン搭載地表計測技術、衛星測位の安定利用に不可欠な宇宙環境計測技術、高い精度を持つ時刻同期技術をご紹介し、将来のドローン運用が更に安心・安全に運用できるようお役に立ちたいと思います。
MPS-5 講演概要
近年、ドローンや空飛ぶクルマなどの新しいエアモビリティの社会実装に向けた動きが加速しており、大阪・関西万博では空飛ぶクルマの運航が計画されている。JAXAは、この動きを技術的に支えるため、低高度を飛行するドローン・空飛ぶクルマ・既存航空機の運航を統合的に管理する運航管理システムの開発、および自動化により運用が容易で長距離・長時間飛行ミッションに適用可能な高性能小型無人機の開発を進めている。
EP-4 講演概要
KDDIスマートドローンは、"叶えるために、飛ぶ。"のミッションのもと、モバイル通信ネットワークを活用した遠隔操作ドローン(スマートドローン)で、お客様の願いを叶えることを目指しています。
本セッションでは、当社が導入を推進しているさまざまな産業分野や自治体でのDX最新事例に加えて、さらなる社会課題の解決に向けた新サービスや取り組みについてご紹介します。
MPS-6 講演概要
農業資材散布用のドローン開発・量産・販売を行ってきた経験から、農業分野におけるドローン利活用の実際を紐解き、現時点での限界と未来展望をお話しいたします。また、ドローン前提社会のなかで、ドローンと掛け合わせる+αの技術としてAI技術など農業分野での最新の取り組みも触れてお話いたします。